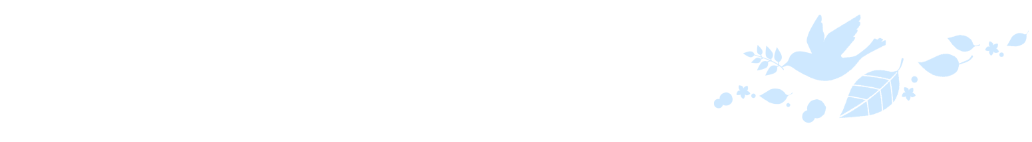- [2025年2月21日]
- ID:5069
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

画像:霞村土地法典
昭和10年4月5日発行 非売品
地番(住所)とその土地の面積(たぶん坪数)が記載されている今の住宅地図みたいなもので、配布されているので旧家には残っていると思われます。
※青梅市自治会連合会第八支会 創立50周年記念誌 (2016年発行)p.52「霞村土地法典」より抜粋
第八支会を中心とした地域の沿革(前史)
- 寛元年間(1303〜1305):師岡神社創建
- 南北朝時代(1300年代後半):城山に築城される(城主、城の名は不明)
- 文亀年間(1501〜1504):この頃、師岡城は勝沼城と呼ばれ、三田氏宗が治める。三田氏宗は、根ヶ布の天寧寺を開く。
- 天文1(1532):天寧寺三世霊陰宗源和尚が光明寺を開く
- 永禄7(1564):北条氏照の武将師岡将景が勝沼城主となり、城の名を師岡城に改める。
- 天正2(1574):師岡将景が、姉妙光禅尼のために寺院(後の妙光院)を創建。
- 天正18(1590):6月、師岡城が豊臣軍に責められて落城、師岡城下に悪疫大流行。天寧寺八世正翁長達和尚が六万薬師堂を創設。
- 元和1(1615):師岡将景が大阪夏の陣で戦死、師岡城廃城。
- 正徳3(1713):虎柏神社(創建は崇神天皇のころ)の現在の本殿再建。
- 寛保1(1741):師岡観音堂本尊准胝観音が作られる。
- 明治7(1874):10月24日、上師岡村と下師岡村が合併して師岡村となる。
- 昭和7(1932):11月、青梅電気鉄道、東青梅停留場が開業。
※青梅市自治会連合会第八支会 創立50周年記念誌 (2016年発行)p.65「第八支会を中心とした地域の沿革」より抜粋
第八支会を中心とした地域の沿革(第八支会設立前)
- 昭和27(1952):4月1日、天寧寺跡境域と勝沼城跡が都の史跡指定を受ける。
- 昭和29(1954):9月、師岡地内の上水道配水鉄管埋設工事竣工
- 昭和30(1955):4月5日、市立第三小学校師岡分校を第四小学校に編入。
- 昭和32(1957):9月、大塚山に第二水源配水池完成。
- 昭和36(1961):3月12日、第四小学校新光社落成式に伴い、師岡分校廃止。
- 昭和38(1963):7月、師岡区画整理地内第1号として完成した公園が「六万公園」と名付けられる。
- 昭和39(1964):6月5日、市内初の鉄骨作りの「屋内運動場」四小に完成。
※青梅市自治会連合会第八支会 創立50周年記念誌 (2016年発行)p.66「第八支会を中心とした地域の沿革」より抜粋
第八支会のはじまり(昭和中期から現在)
- 昭和41年4月:第三支会が発展してきたため、東青梅地区の11自治会1,917世帯をもって第八支会が発足する。(東1、東2の1、東2の2、東3、東4、東5、東6、根ヶ布、下師岡上、下師岡下、吹上)
- 昭和45年4月:多摩団地自治会が発足し12自治会となる。2,817世帯
- 昭和46年4月:旭ヶ丘自治会が発足し13自治会となる。2,886世帯
- 昭和47年3月:吹上自治会は第三支会へ編入し12自治会となる。3,170世帯
- 昭和48年4月:下師岡上自治会が師岡1丁目自治会と名称変更、下師岡下自治会が師岡町2丁目自治会と名称変更。師岡3丁目自治会が発足し13自治会となる。3,203世帯
- 昭和50年4月:緑が丘自治会が発足し14自治会となる。3,263世帯
- 昭和52年4月:師岡3丁目自治会は師岡3・4丁目自治会となる。3,530世帯
- 昭和58年4月:グリーンサイド東青梅自治会発足し15自治会となる。4,353世帯
- 昭和59年4月:緑が丘自治会は解散となる。14自治会となる。4,440世帯
- 昭和60年4月:バームハイツ河辺自治会が発足し自治会数15自治会となる。4,831世帯
- 平成10年4月:ハイホーム東青梅自治会が発足し16自治会となる。6,814世帯
- 平成28年4月:16自治会、7,753世帯
※青梅市自治会連合会第八支会 創立50周年記念誌 (2016年発行)p.9「(2)第八支会の歴史」より
お問い合わせ
青梅市自治会連合会 第8支会(東青梅市民センター)
電話: 0428-24-8110
ファクス: 0428-24-3842
電話番号のかけ間違いにご注意ください!